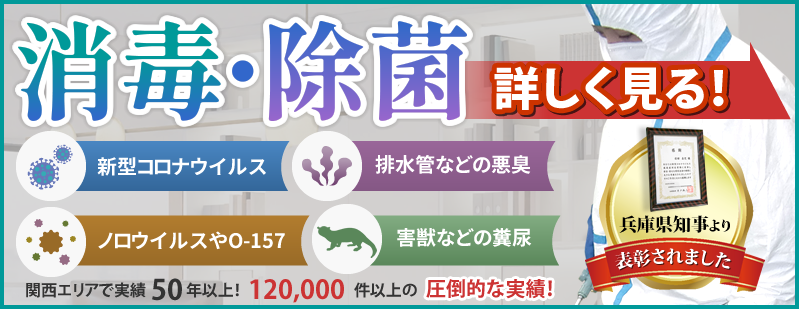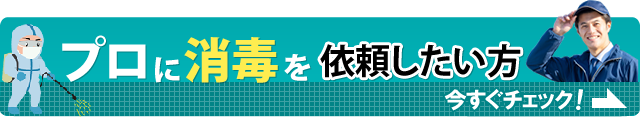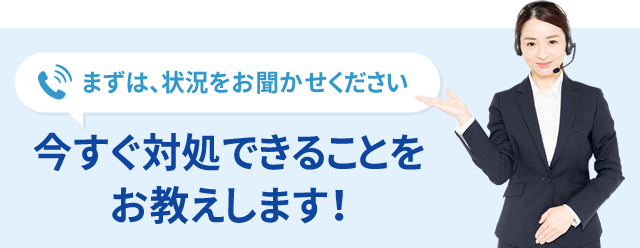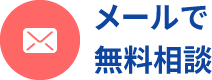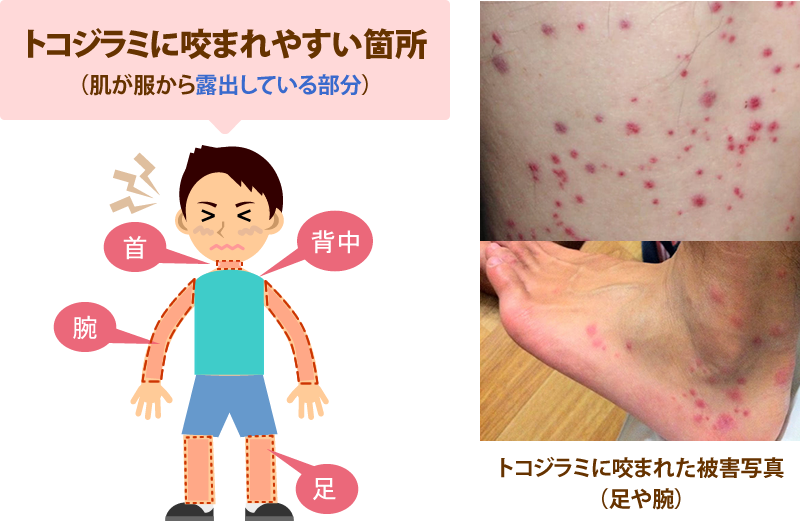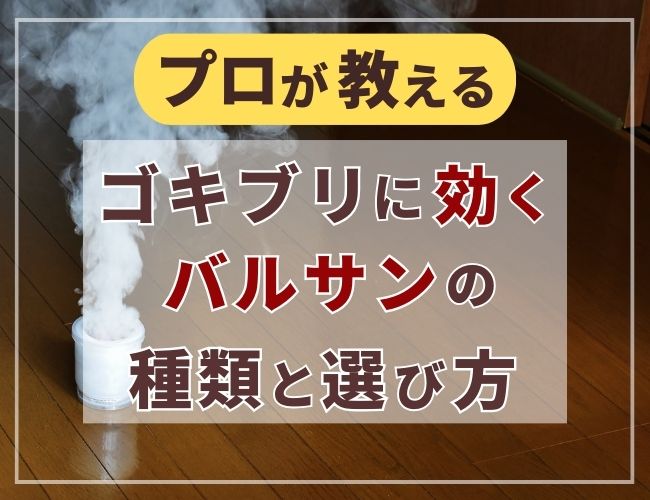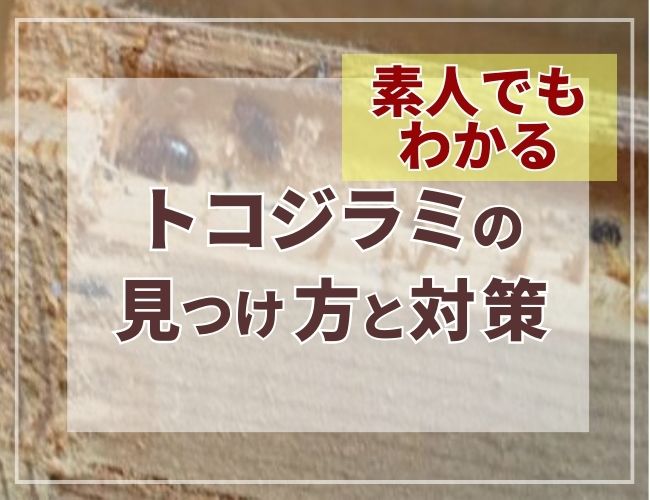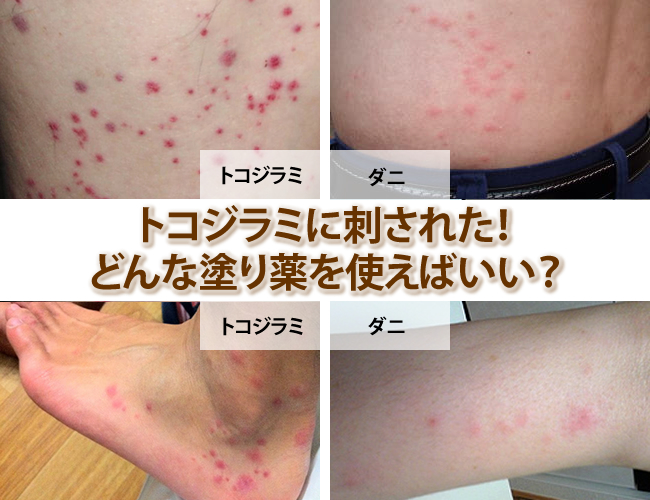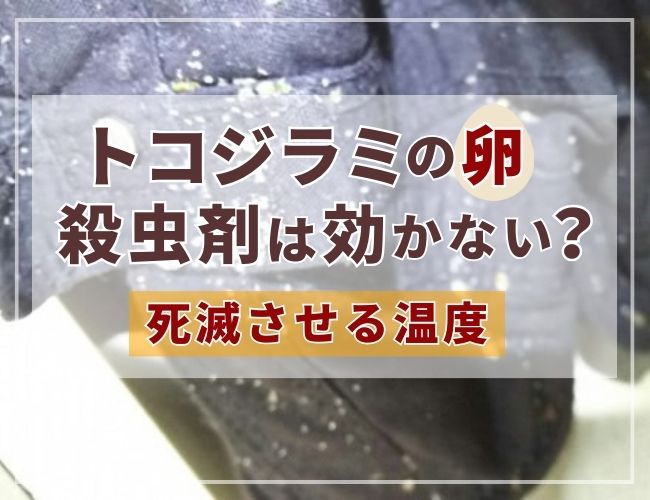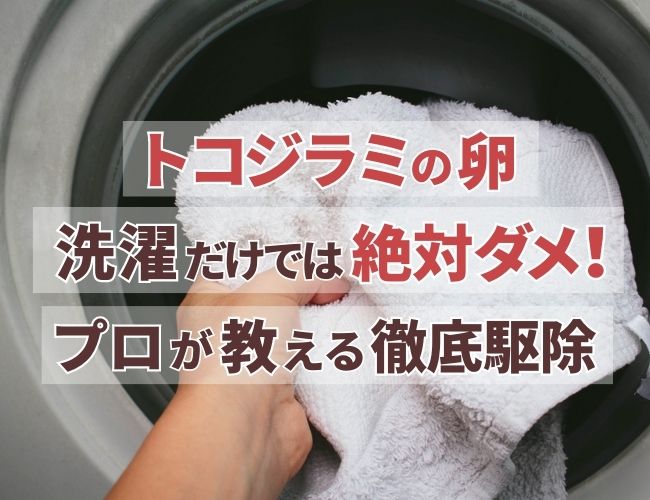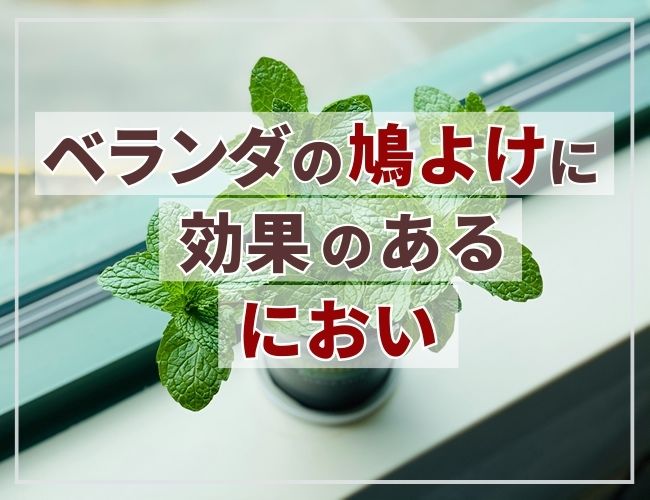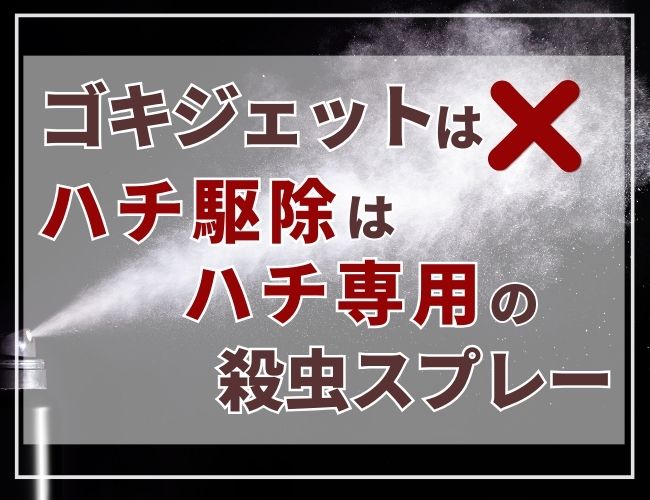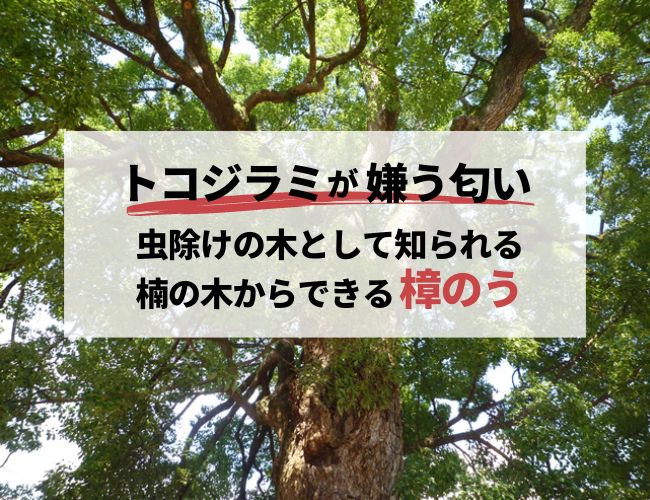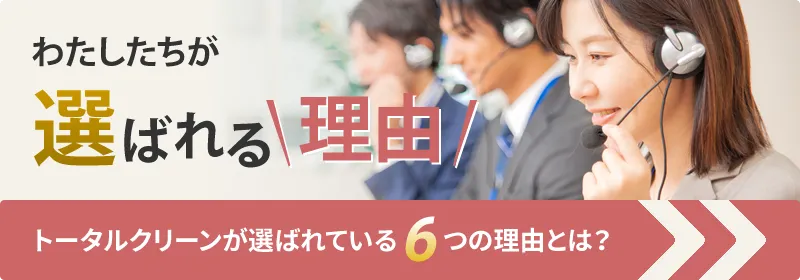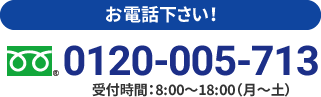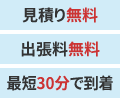毎年冬になると多発するノロウイルス。特に飲食店では、感染拡大を防ぐための対策が重要です。
飲食店がノロウイルスによる食中毒と認定されてしまった場合、通常3日間程度の営業停止処分などを受けてしまいます。
もちろん、営業停止処分以上に怖いのが、顧客離れ。
この記事では、ノロウイルスの特徴から正しい消毒方法、予防のポイントまでを詳しく解説します。
Table of Contents
ノロウイルスの特徴とは?
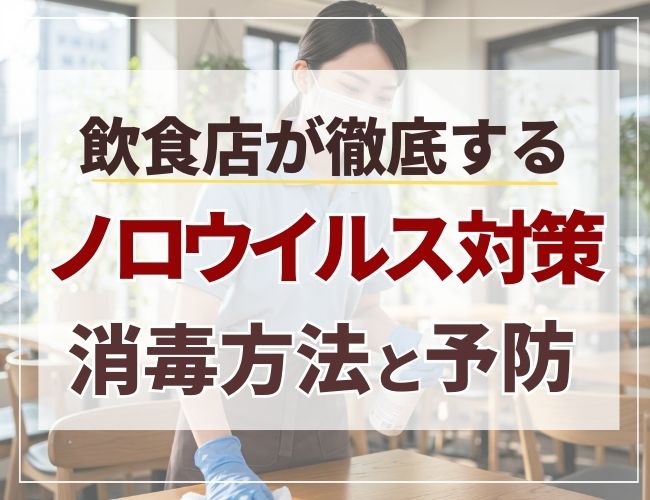
ノロウイルスは非常に感染力の強いウイルスで、たった10~100個のウイルス粒子でも感染するといわれています。主な感染経路は以下のとおりです
- 感染者の手や嘔吐物・便を介した接触感染
- 汚染された食品(特に二枚貝)
- ウイルスが付着した器具やドアノブなどの共用物
特に飲食店では、お客様とスタッフの安全を守るため、迅速かつ正確な対応が求められます。
ノロウイルスにアルコール消毒は効かない?
結論から言えば、一般的なアルコール消毒剤ではノロウイルスの除去に不十分な場合があります。
ノロウイルスは「ノンエンベロープウイルス」と呼ばれ、脂質膜(エンベロープ)を持たないため、アルコールが内部に浸透しにくく、消毒効果が限定的とされています。
そのため、感染対策には「次亜塩素酸ナトリウム(家庭用漂白剤など)」や、「ノロウイルスに対応した専用の消毒剤」の使用が推奨されます。
ただし近年では、ノロウイルスに対して効果を示すアルコール製剤も開発されており、状況に応じて選択肢が広がってきています。
また石けんにも、ノロウイルスを直接的に殺菌する効果はありません。
ただし、石けんで手を洗うことで手の表面についたノロウイルスを物理的に落としやすくなります。
感染予防の基本は手洗いですので、直接効果がないからと言って疎かにはしないでください。しっかりと石けんで洗うことで、手や指にウイルスが残るリスクを大幅に減らせます。
ノロウイルスの消毒方法
次亜塩素酸ナトリウム
ノロウイルスを消毒(失活化)するには、次亜塩素酸ナトリウムを使うのが、とても効果的です。
消毒したい対象のモノを洗浄した後、次亜塩素酸ナトリウムをたっぷりと浸すように使うことでノロウイルスを除去することができます。
例えば、調理台の上だったら、まずは洗剤で洗浄をしたあと、水で洗い流します。次に次亜塩素酸ナトリウムを調理台がしっかりと濡れるくらい撒いてから拭き取るのが、ノロウイルスを不活化するコツです。
熱消毒
次亜塩素酸ナトリウムがない場合でも、熱湯が有効です。
特に小さな調理器具、例えば包丁、お皿やフォークなどの食器類であれば、鍋などにお湯を張って煮沸消毒をするのが、簡単な方法です。
ふきんやタオルなども同じ方法で消毒できます。
なお、ノロウイルスを失活化するには、食品や調理器具の中心部が85~90℃で90秒以上の加熱が推奨されます。
実践!ノロウイルス消毒の正しい手順
1.嘔吐物や便の処理手順
- 手袋・マスク・エプロン・ゴーグルを着用(使い捨てが望ましい)
- 嘔吐物はペーパータオルで静かに拭き取り、密封できる袋に入れて廃棄
- 床や周辺を次亜塩素酸ナトリウムで拭き取る(濃度0.1%が目安)
- 使用した器具やモップも同様に消毒
※処理中は換気を行い、作業者以外を近づけないことが重要です。
2.手指やドアノブの消毒
- 手指:石けんと流水で30秒以上の手洗い → アルコール消毒も併用
- ドアノブやテーブル:0.02〜0.05%の次亜塩素酸ナトリウムで拭き取り消毒
消毒の際に注意するポイント
上記でノロウイルスを消毒する方法について解説しましたが、消毒を実施する際に注意するポイントがあるので簡単に説明します。
有効塩素濃度の確認
市販の漂白剤で消毒液を作る(次亜塩素酸ナトリウム)場合は濃度の調整が必要です。(例:原液6%なら水で60倍希釈で0.1%)
<例>
・嘔吐物・便などの処理:0.1%(1000ppm)
・ドアノブや調理器具などの日常消毒:0.02%(200ppm)
次亜塩素酸ナトリウムはたっぷり使う
次亜塩素酸ナトリウムで消毒をする際は、たっぷりと使うことを意識してください。
どうしても、アルコール消毒の感覚で消毒をしようとする方が多いですが、それでは足りません。
しっかりと消毒するには、対象のモノがびしょびしょになるくらい、多めの次亜塩素酸ナトリウムを使いましょう。
使い捨て資材を使用する
感染拡大を防ぐために、可能な限り使い捨て用品を使いましょう
しっかりと汚れを落としてから消毒する
ノロウイルスが含まれるおう吐やふん便の他、消毒をしたいモノに食材や油汚れなどが付着している場合は次亜塩素酸ナトリウムの消毒効果が減退します。
次亜塩素酸ナトリウムで消毒をする前に、そういった有機物をしっかりと取り除き、清掃をしてから消毒をするのがノロウイルスを除去するコツです。
素早く掃除して消毒する
ノロウイルス感染者のおう吐物やふん便は素早く掃除して、消毒をしてください。
ノロウイルス感染者のおう吐物やふん便には大量のウイルスが含まれていて、二次感染を引き起こす主な感染源となっているからです。
また、おう吐物やふん便が乾くとウイルスが空気中に舞い上がりやすくなり、飛沫核感染の原因にもなります。
感染拡大を防ぐには、おう吐物やふん便の迅速な処理がとても重要です。
金属の腐食に注意
次亜塩素酸ナトリウムは金属を傷めることがあるため注意してください。
予防:専用の調理器具を用意する
ノロウイルスの感染源として、有名なのが二枚貝。
二枚貝とは、カキ、シジミ、アサリやハマグリなど、殻を二つ持つ貝の総称です。
これらの食材を調理する際は、専用のモノを用意することでこまめな洗浄や消毒ができます。
他の食材への二次感染防止のためにも、二枚貝を調理する場合は、ぜひ専用の調理器具を用意しましょう。
飲食店経営者ならノロウイルスの感染経路を知っておこう
ノロウイルスの感染には3種類の経路があります。
- 接触感染
- 飛沫感染
- 飛沫核感染(エアロゾル感染)
飲食店経営者の方なら、必ず知っておきましょう。
ノロウイルスの感染経路① | 接触感染
ノロウイルスの1番オーソドックスな感染経路が接触感染です。
感染者のふん便、吐しゃ物に手などが触れて感染するのが接触感染です。
他にも既に汚染されたモノに触れたり、ノロウイルスのいる貝を食べたりして感染するのも接触感染にあたります。
ノロウイルス感染者の吐しゃ物を片付けるときは、しっかりと手などを防護して実施するのが感染しないコツです。
またトイレに入る際、ドアノブなどからも感染する可能性があるので注意してください。
ノロウイルスの感染経路② | 飛沫感染
ノロウイルス感染者がおう吐をした際に、その飛沫が飛んで吸い込んだりすることで感染するのが飛沫感染です。ノロウイルスに感染して具合が悪くなった患者に付き添って感染してしまうというケースがあります。
ノロウイルスの感染経路③ | 飛沫核感染
ノロウイルスは、乾燥した吐物や便からウイルスが空気中に舞い上がり、吸い込むことで感染する“飛沫核感染”も報告されています。
この飛沫核感染こそが、気をつけていてもノロウイルスに感染してしまう大きな原因の一つです。
ノロウイルスに汚染されたふん便やおう吐物を片付けるときは、ウイルスが舞い上がらないように丁寧に処理することが大切です。
感染予防のためにも、慎重な対応を心がけましょう。
飲食店でのノロウイルス感染を防ぐ具体的な対策
ノロウイルスの消毒方法とそのコツ、感染経路などの他、最後に具体的な感染対策を紹介します。
ここでは主なものを5つ。
- 手洗いが基本
- ペーパータオル
- 専用の調理器具
- 十分な熱処理
- 従業員の体調把握
飲食店でのノロウイルス感染対策① | 手洗いが基本
石けんが、直接ノロウイルスを失活化することができないとしても、やはり手洗いはとても重要です。
なぜなら、手洗いは手指についたノロウイルスを減らす最も有効な方法の1つだからです。
内閣府食品安全委員会の資料「ノロウイルスの消毒方法」によると、有効な手洗い方法は、石けんやハンドソープを使った30秒間のもみ洗いと15秒間の流水でのすすぎを複数回くり返すことです。2回繰り返すと、ノロウイルスの残存率を約0.0001%まで減らすことができたとする実験結果があります。
飲食店従業員の方には、小まめな手洗いを心がけてもらいましょう。出勤時やトイレの後はもちろん、休憩の後なども忘れがちなので注意が必要です。
飲食店でのノロウイルス感染対策② | ペーパータオル
コロナウイルス流行の影響で、多くの飲食店では、手洗い後はペーパータオルを使用するようになっていると思います。
しかし、従業員用には、未だに使いまわしのタオルを使用しているところも見受けられます。
ノロウイルス感染者がいるとタオルを介して感染する可能性がありますので、まだ タオルなどを利用している場合は、必ずペーパータオルに切り替えましょう。
飲食店でのノロウイルス感染対策③ | 専用の調理器具
「ノロウイルスを消毒するコツ」でも記載しましたが、二枚貝を取り扱う飲食店では、必ず専用の調理器具を用意しましょう。
専用の調理器具を使用することで、他の食材への二次感染を減らすことができます。また、専用にすることで、普段から意識的に洗浄・消毒をしっかりとすることができます。
飲食店でのノロウイルス感染対策④ | 十分な熱処理
ノロウイルスは食品や調理器具の中心部が85~90℃で90秒以上の加熱が推奨されます。これは食器やまな板などの調理器具だけでなく、二枚貝などの食材にも言えることです。
ノロウイルス流行時は、可能であればしっかりと食材の中心部まで火を通すようにすることで、ノロウイルスへの感染を防ぐことができます。
実際、加熱するとなると温度がしっかりと測れない、測れる場合でも誤差などを考えると、少し余分に加熱すると安心です。
飲食店でのノロウイルス感染対策⑤ | 従業員の体調把握
従業員の体調を把握することも大事です。
ノロウイルスの特徴として、感染すると、おう吐、下痢、腹痛、また発熱を伴います。
このような症状が出た従業員には必ず休んでもらうようにしましょう。
医療機関で簡単に検査することも可能ですので、すぐに受診をしてもらうことも大事です。
感染が確認された場合は、1週間程度の期間、自宅で療養してもらってください。
ノロウイルス感染が疑われる場合は、症状消失後も最低2日間は出勤を控え、必要に応じて検便などで陰性確認を行いましょう。
ノロウイルスは飲食店運営にとって新型コロナウイルスより怖い
飲食店にとってノロウイルスは、いまや新型コロナウイルスよりも怖い存在かもしれません。
当然、コロナウィルスの感染予防はしっかりとする必要がありますが、どうしても防ぎきることはできません。
そして、万が一かかってしまったとしても対策をしていた上での感染であれば、「仕方ない」のも事実です。
一方、ノロウイルスの場合、飲食店を発生源として感染が広まった場合、「仕方ない」と許容されづらいです。
実際、営業禁止処分、営業停止処分などは行政処分です。
国が飲食店に対してノロウイルスの感染予防・防止に強い責任感を求めていることがわかります。
また、営業停止処分となれば、顧客離れが進みます。一旦、離れたお客さんが戻ってくるまでにはイバラの道が待っているでしょう。
ノロウイルスの感染は予防・防止できる
ノロウイルスの感染は本記事で解説した対策を実施すれば、予防・防止することができます。
まずは今日からできる対策を実施してみましょう。
それだけで劇的に飲食店でのノロウイルス感染を減らすことができるはずです。
また、多数の実績を持つ知識豊富なプロに相談してみるのもおすすめです。
多くの専門業者では、無料で相談することができますので、まずは無料相談を利用してみてはいかがでしょうか?