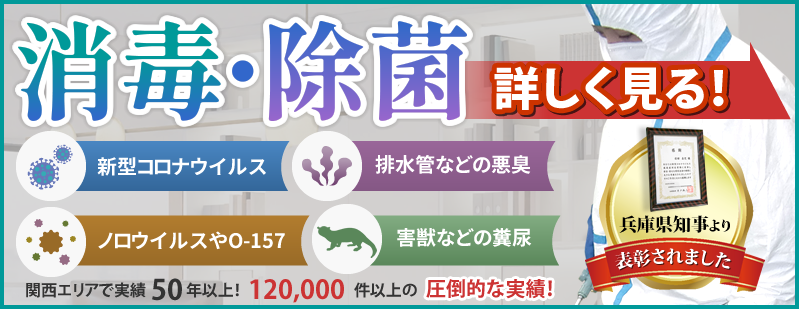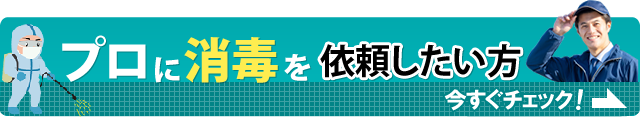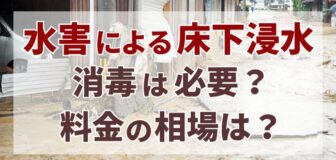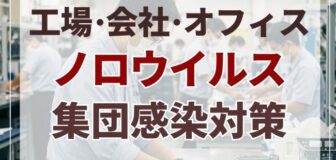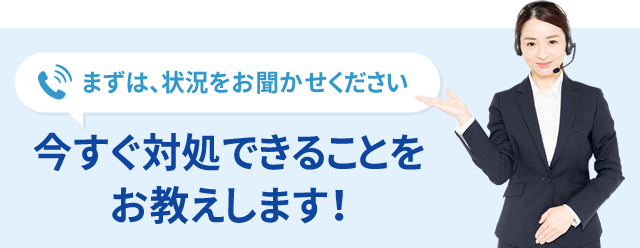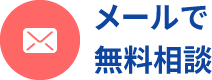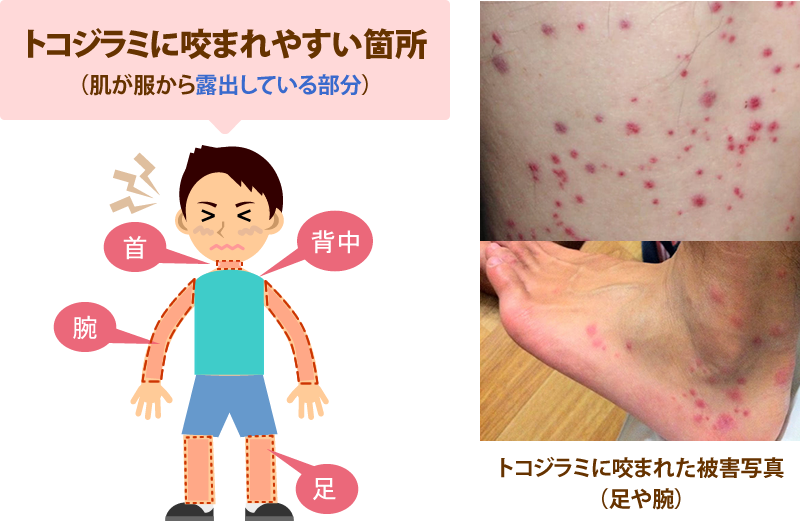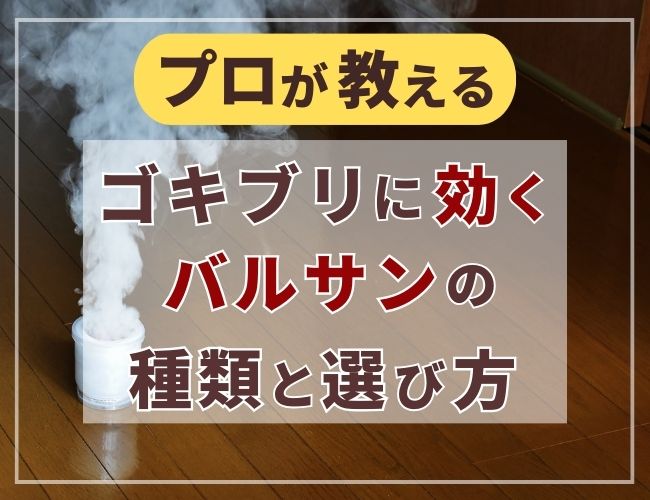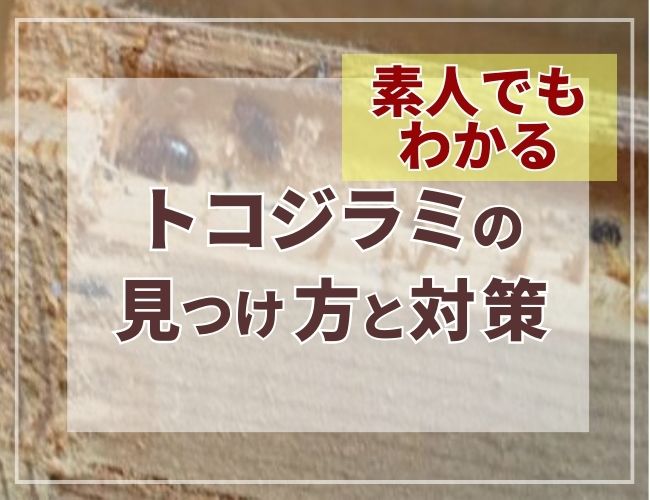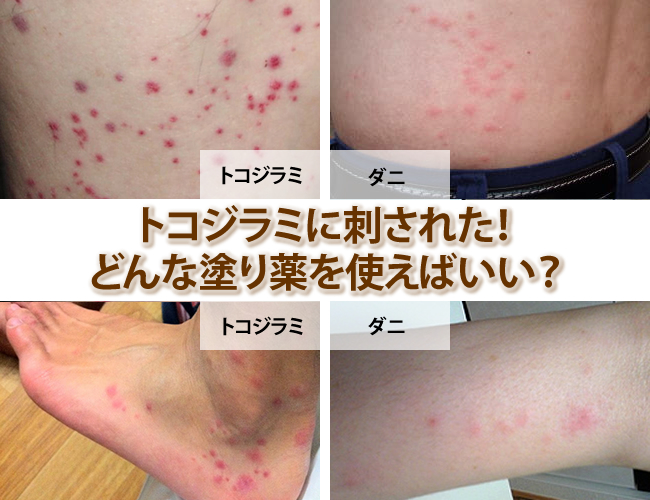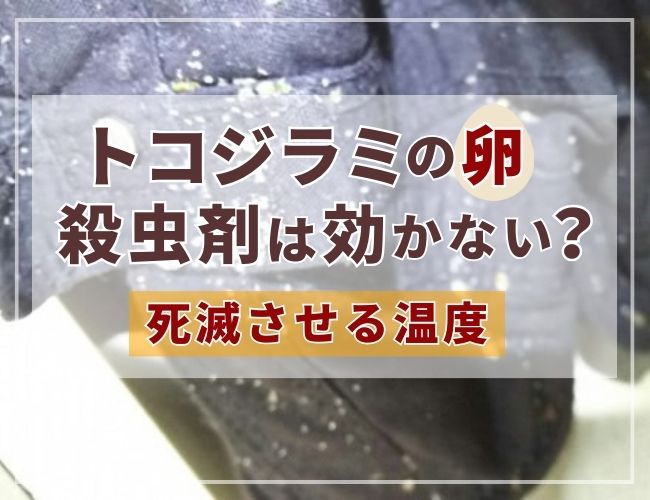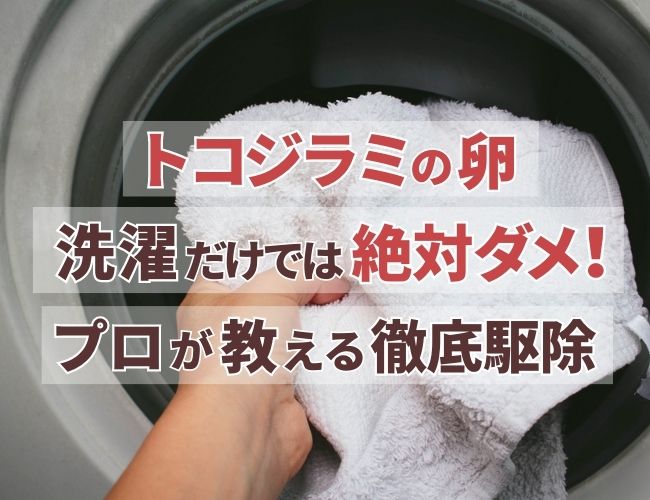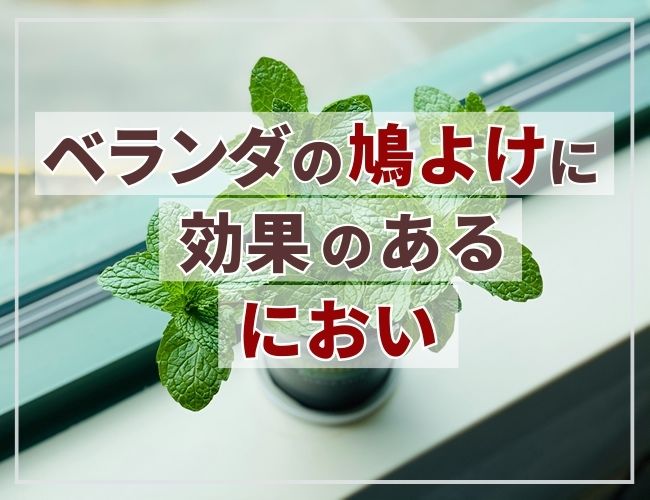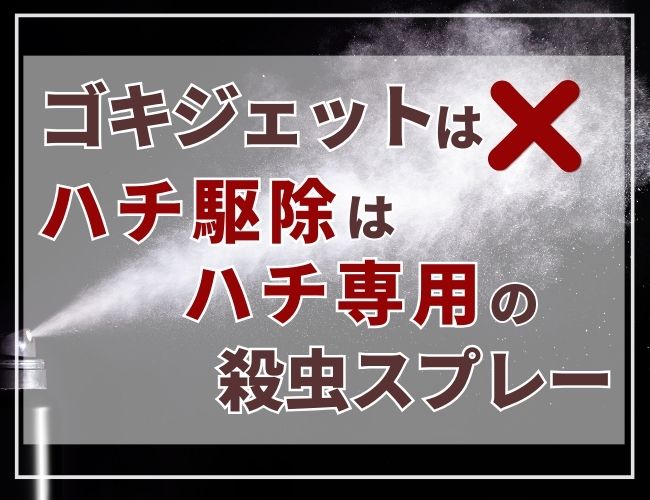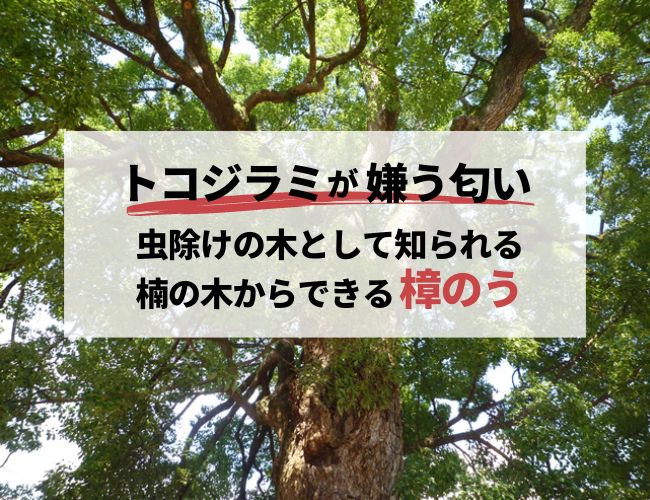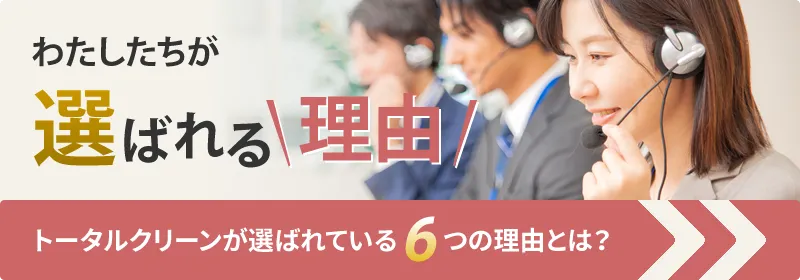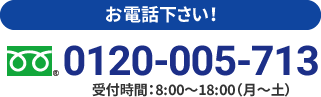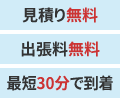毎年夏場を中心に発生が増えるO-157(腸管出血性大腸菌)は、わずかな菌数でも重い症状を引き起こす危険な食中毒菌です。
特に乳幼児や高齢者では重症化リスクが高く、家庭や施設での衛生管理がますます重要となっています。
この記事では、最新の発生状況や国内外の事例を踏まえ、O-157の感染経路や予防策、効果的な消毒方法について分かりやすく解説します。
日々の生活で実践できる対策を知り、大切な家族や自分自身を守るための参考にしてください
Table of Contents
O-157は感染力が非常に強く危険
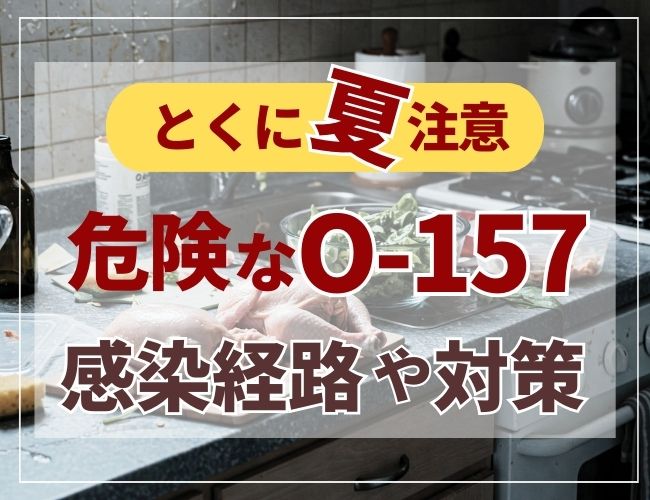
O-157はとても危険な大腸菌です。
誤解されがちですが、大腸菌は人間や動物の腸内に普通に存在します。そして、そのほとんどが無害です。
しかし、大腸菌の中にはいくつか悪さをする菌がいるのです。
その代表選手がO-157。
O-157は、強力なベロ毒素を産生する腸管出血性大腸菌の一種で、感染すると腹痛や下痢、血便、発熱、嘔吐などの症状が現れます。
多くの場合、症状は数日から10日ほどで軽快しますが、特に乳幼児や高齢者では重症化しやすく、溶血性尿毒症症候群(HUS)や脳症などの重篤な合併症を引き起こすことがあります
O-157(腸管出血性大腸菌)は、非常に強い毒素を産生し、重症化や合併症のリスクが高い食中毒菌です。
幼児や高齢者は特に注意が必要です。
近年も米国で大規模な食中毒事件が発生しており、衛生管理や予防策の徹底が改めて重要視されています。
O-157の主な感染経路
O-157は飲食物などを口にして感染するケースがほどんどです。
菌に汚染された飲食物を摂取するか、感染者の糞便で汚染されたものが口に入るなどして感染します。
また、O-157は他の食中毒を引き起こす細菌(100万個~)などと違って、わずか100個程度の少量の菌でも感染するのが特徴です。
O-157の主な感染経路は以下のとおりです。
- 汚染された食品(特に牛肉や生野菜)
- 感染者の便や手指を介した接触感染
- 井戸水などの飲料水
1.汚染された食品(特に牛肉や生野菜)
O-157の感染源として有名なのが牛の肉。牛などの反芻動物が保菌していることが多く、肉や内臓、またはその糞便で汚染された食品が感染源となります。
牛レバーの生食が禁止されたのは、このO-157などの腸管出血性大腸菌による食中毒が原因です。
厚生労働省が牛レバーに付着している可能性のあるO-157を問題視して、安全性を確保するためにそのように判断したからです。
2024年には米国でスライスオニオンが原因とみられる大規模食中毒が発生しました。
2.感染者の糞便
O-157に感染した人の糞便には、O-157が多く含まれます。
その糞便を処理する過程で、手などに菌が移り、そこから口内に菌が入り込んで感染を引き起こします。
感染者が使用したトイレやドアノブ、調理器具などを介して手指に菌が付着し、そこから口に入ることで感染します。
3.井戸水
井戸水にもO-157が含まれていることがありますので気をつけてください。
掘削深度の浅い井戸では、特に地上部から流れ込む水の影響を受けやすいため、その水質も変化しやすいです。
牛舎や豚舎の近くの井戸から汲み上げた水を使用した集団食中毒の例や、井戸水を飲料水として使っていた幼稚園での痛ましい事件など、井戸水からO-157が検出された事例もあります。
O-157の感染対策と消毒方法【2025年最新版】
O-157は非常に強い毒を出す怖い菌ですが、消毒や感染対策は比較的シンプルです。
基本的には通常の食中毒対策をすれば問題ありません。
以下に感染対策と消毒方法について解説します。
- 食品の十分な加熱
- 徹底した手洗い
- 調理器具・食器の管理
- アルコール・塩素系消毒剤の活用
- 食品の適切な保存
1.肉類や魚介類は中心部まで75℃で1分以上加熱
O-157は加熱により比較的容易に消毒できます。
なぜならO-157は熱に弱く、75℃で1分以上加熱すると死滅するからです。
肉や魚はもちろん、野菜なども熱を加えることで安心して食べることができます。
特に肉料理は、中心部までしっかりと熱を加える意識で調理しましょう。
牛レバ刺しが国によって提供が禁止されたのは、熱を加えないで食べるからです。
2.徹底した手洗い
どんな菌やウイルスであれ、感染予防の基本はこまめで入念な手洗い。
調理を始める前、生ものを扱う前後、食事前など、都度手を洗うことは自分でできるもっとも簡単な食中毒対策です。
もちろんO-157の感染対策にも有効です。
3.調理器具・食器の管理
包丁、まな板、トレーなどの調理器具は使ったら都度洗いましょう。
特に肉魚などを扱った場合は忘れずに。
万が一、O-157に汚染された食材を扱った場合でも、調理器具を洗っていれば他の食材に付着するのを防げます。サラダ用の野菜など加熱しない食材を扱うときに特に大事です。
また、初めから調理器具を肉魚用と野菜用などと分けておくのも、都度洗う手間をかけられないという場合に有効な手段です。
4.食品の適切な保存
食品の保存には気をつけてください。
O-157は10℃以下で増殖が穏やかになり、マイナス15℃以下で増殖が停止します。
O-157菌が冷蔵庫、冷凍庫で死滅することはありませんが、増殖は抑えられます。
使い切らない冷凍品を解凍してまた戻すなど、解凍と再冷凍の繰り返しは避けましょう。
とくに肉魚類には注意してください。
5.アルコールの活用
アルコールや塩素系の消毒薬もO-157を消毒するのに効果があります。
アルコールを手にしっかりと塗りこむ、次亜塩素酸ナトリウムで使用済みの食器やふきんをつける、それによってO-157を死滅させることができます。
アルコール消毒の有効性と使用方法
- 濃度: 70%以上95%以下のエタノールが推奨されています。
- 使用方法: 手指に十分な量を取り、乾燥するまで擦り込むことが重要です。
- 注意点: アルコールに過敏な方は使用を控えること、引火性があるため火気の近くで使用しないこと、空間噴霧は絶対に行わないことが強調されています。
6.次亜塩素酸ナトリウムの使用方法と注意点
次亜塩素酸ナトリウムの希釈液はハイターやブリーチなどで作ることができます。
その際、用途や現役の濃度によって希釈する割合が変わるので注意が必要です。
原液の濃度に併せて水で希釈して作ってください。
次亜塩素酸ナトリウム消毒液 希釈表(1L作成の場合)
| 原液の濃度 | 0.01%溶液の作り方 | 0.02%溶液の作り方 |
|---|---|---|
| 1% | 原液10ml + 水990ml | 原液20ml + 水980ml |
| 6% | 原液1.67ml + 水998.33ml | 原液3.33ml + 水996.67ml |
| 12% | 原液0.83ml + 水999.17ml | 原液1.67ml + 水998.33ml |
使用時の重要ポイント
- 汚染レベルによる濃度選択が大切です。
- 通常の消毒(食器・調理器具) → 0.01-0.02%
- 嘔吐物/便の処理 → 0.1%以上
有機物の影響
血液や汚れがある場合、消毒前に物理的除去(ペーパータオル等で拭き取り)が必要です。
有機物が残っていると消毒効果が最大1000分の1まで低下するため、消毒前にしっかりと拭き取ってください。
使用期限
作成後24時間以内に使用(特に低濃度溶液は分解が早い)してください。
遮光容器で冷暗所保存しましょう。
注意事項
- 金属腐食性があるため、消毒後は水拭き
- 他の酸性洗剤と混合禁止(塩素ガス発生の危険)
- 手指消毒には不向き(皮膚刺激性あり)
次亜塩素酸ナトリウムについて、もう少し詳しく知りたい方は以下の記事も参考にしてみてください。
最新の注意点・トピック(2024~2025年)
米国での集団食中毒事件から学ぶ衛生管理の重要性
2024年、米国のマクドナルドでスライスオニオンが原因とされるO-157集団感染が発生。
工場の衛生管理不備(清掃不足・記録管理の不備・手順未徹底)が指摘されました。
日本でも食品工場や飲食店での衛生管理徹底が求められています。
出典:アメリカ食品医薬品局 (Food and Drug Administration)
WHO「5つの食品安全キー」も参考に
「清潔にする」「生と加熱済みを分ける」「十分に加熱する」「安全な温度で保存」「安全な水と原材料を使う」が国際的な基本指針です。
出典:WHO(World Health Organization)
まとめ│O-157の感染予防は「基本の徹底」
O-157は少量でも感染する強力な菌ですが、日々の基本的な衛生習慣と適切な消毒・加熱で十分に予防できます。
特に2024年の事例からも、「手洗い」「加熱」「交差汚染の防止」「適切な消毒」が改めて重要であることが示されています。
ご家庭でも、職場や施設でも、今一度対策の見直しをおすすめします。